特許法の語呂合わせ一覧(移転、142条の除斥忌避)
目次
補償金請求権で不準用な条文
補償金請求権の趣旨
補償権請求権の趣旨は出願公開制度に大きく関係しています。青本にも次のように書かれています。
出願公開は、特許出願の内容を一般公衆に知らせるものであるから、第三者はその内容を実施することが可能になる。そこで自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を塡補するためにその実施をした者に対する補償金請求権を認めることとした。
引用元:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕
つまり、出願公開制度によって発明が公開されてしまうので、悪い人がその公開を見て真似して発明を実施できてしまいます。一方で出願人は特許権侵害として差し止め等ができるのは特許権の設定登録後ですので出願人はその悪い人をとめることができません。
そこで 補償権請求権 をみとめ、そういった悪い人に対してお金を請求できるようにしているのです。
補償金請求権の効果ですが
その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である 場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができます。
ここで特許侵害と大きく異なるのは損害賠償のように、損害の額を請求できるのではなく請求できるのは実施料相当額であることです。
補償金請求権で不準用な条文の覚え方
補償金請求権においては損害賠償の特例が多く準用されています。
短答試験では、 損害賠償の特例の中で補償金請求権に準用されていないものが良く問われます。
受験生は補償金請求権ではなにが不準用だったかを覚えなくてはなりません。ただしこれは補償金請求権の内容と趣旨がわかっていればある程度解けます。
例えば、補償金請求権は権利化前の行為について請求するものですので100条の差止請求が不準用なのは当然ですね。
その他にも102条、103条、104条の4、105条の3、106条、168条1項2項が不準用です。
たくさんありますし、後半は趣旨から考えても準用か不準用かの答えを出すのが難しいです。
補償金請求権で不準用な条文の 語呂
ここで語呂を紹介したいと思います。
兄さん妊娠不準用!
にー 102条(損害額の推定等)
さん 103条(過失の推定)
にん 105条の3(相当な損害額の認定)
しん 106条(信用回復の措置)
104条の4は不準用ではあるのですが、104条の4の条文において
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後にとあるので実際には104条の4の適用があります。
168条1項、2項については上記の語呂とは別で覚えましょう。
3名、3人又は5人、5人?判定や審判の人数の覚え方
特許異議の申立てについての審理及び決定は三人又は五人の審判官の合議体が行うことになっていますね。特許法第114条の規定です。この人数は 特許異議の申立ての審理及び決定では 三人又は五人 になっていますが、他の条文とごっちゃになってしまい短答で聞かれて間違ってしまうことがあります。
特許法では人数が出てくるものとして次の規定があります。
判定と鑑定
判定と鑑定については、三名の審判官が指定されて行うことになっています。( 71 条、71条の2)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
引用元:特許法第第七十一条第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
引用元:特許法第第七十一条の二
させなければならない となっている点にも注意が必要です。短答試験ではこういった細かいところも狙われます。例えば次のような問題もあり得ます。
特許庁長官は、判定の求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせることができると特許法に規定されている。
答え…×

ちなみに「鑑定の嘱託」とは民事訴訟法218条に出てくる手続きです。
民事訴訟法第二百十八条
。
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する
引用元:民事訴訟法第二百十八条
どーでもよい話ですが判定と鑑定だけは「名」が使われています。他は「人」が使われています。
一応日本語的には「人」と「名」は意味が違うようです。個人を特定できる場合は「名」を使うようです。一方で個人を特定できない場合は「人」が使われるようです。
ただし、これらの条文については深い意味はないと思います。
異議申し立ての審理及び決定、審判
異議申し立ての審理及び決定、審判については、三人又は五人の審判官の合議体 が行います。(第114条1項、第136条1項)
奇数になっている理由は、多数決で決めることができるようにするためです。又は となっているところが受験生からするといやらしいですよね。
審決取消訴訟
五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができます(182条の2)。
ここだけ審判官ではなく裁判官なので注意しましょう。人数は5人と最も多くなります。

覚え方
三名 、 三人又は五人 、 五人 の3種類があって混同しやすいです。
表で覚えましょう。

条文が若いものから徐々に人数が増えていくイメージです。判定と鑑定は1セットで3名、異議と審判は1セットで3人又は5人と考えるのも容易でしょう。訴訟は審判官の合議体ではなく裁判官の合議体なので注意しましょう。
実践編 令和3年弁理士試験
【意匠】9-枝4特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
引用元:令和3年度弁理士試験短答式筆記試験問題(https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/document/2021tanto/question.pdf)
意匠ですが考え方は同じです。鑑定なので3名です。よって答えは〇。
【特許・実用新案】20-枝4特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
引用元:令和3年度弁理士試験短答式筆記試験問題(https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/document/2021tanto/question.pdf)
これはちょっと難しいですね。審判についてだから 3人又は5人の審判官の合議体 で即答したいところですが参加の決定まで 3人又は5人の審判官の合議体 で行うのか?
しかし149条3項には参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。とありますので参加の申請に対しても 3人又は5人の審判官の合議体 が行います。
よって答えは〇。
特許権等の移転や放棄についての承諾が必要な場合
特許権の移転において
放火異常(放下移上)
という有名な語呂があります。
これは、登場人物を次のように川上から川下に並べて考えます。
(上)特許権>専用実施権>通常実施権(下)
そして、「放」つまり放棄するには「下」の承諾が必要。「異」つまり移転する際は「上」の承諾が必要であるということを表現した語呂になります。
例を見ていきましょう!
(1)特許権者が特許権を放棄するときは専用実施権者と通常実施権者の承諾が必要です。
放(棄)は下の許可が必要ということですね。
一方で特許権者が特許権を移転するときは専用実施権者と通常実施権者の承諾は不要です。
移(転)上だからです。
(2)専用実施権者が専用実施権を放棄するときは
放(棄)下で下に通常実施権者がいれば通常実施権者の承諾が必要です。
専用実施権者が専用実施権を移転するときは
移(転)上で、上の特許権者の承諾が必要です。
(3)通常実施権者が通常実施権を放棄するときは
放(棄)下で下がいないので誰の承諾も必要ありません。
通常実施権者が通常実施権を移転するときは
移(転)上で、上の特許権者(専用実施権者がいるときは専用実施権者も)の承諾が必要です。
基本的には特許権が放棄されてしまうと、だれでもその発明を実施できてしまうからその下にいる人たちは不利益を受けます。しかし移転されても第三者がその発明を実施できる訳ではないので不利益はないからです。
通常実施権が放棄されても、特許権者はその発明をできる人が1人減っただけで特に不利益はありません。しかし移転されてしまうといかのような不利益があります。
例えば、特許権者が小さな会社でやっとの思いで大きな発明をし下請け会社に通常実施権を許諾し、その通常実施権者(下請け会社)が通常実施権を特許権者よりも1000倍くらい大きな会社に移転してしまった場合。
特許権者がその発明に係る製品を販売するよりもその大きな会社がその発明に係る製品を販売したほうが価格や技術力的に優れる可能性は高く特許権は有名無実なものとなってしまいます。

そしてもう一点
質権者はどうなるのかが気になります。
(上)特許権>特許権の質権者>専用実施権>専用実施権の質権者>通常実施権>通常実施権者の質権者(下)つまり特許権者が特許権を放棄するときは下の承諾が必要ですから質権者の承諾が必要です。
これは語呂がどうこうというよりは、質権を設定している以上人の権利なので勝手に放棄してしまうと問題だからですね。一方、特許権がAさんからBさんに移転されても、質権者の質権はBさんとの間で有効ですので問題はありません。
通常実施権の中で相当の対価を支払わなくてはならないものの語呂
弁理士試験における通常実施権
特許法にはたくさんの通常実施権があります。
発生の場面によって許諾による通常実施権、法定通常実施権、裁定通常実施権があります。
許諾による通常実施権 は、特許権者のAさんがBさんに「発明使っていいよ」と許諾して成立するものなので比較的わかりやすいのですが、通常実施権のなかには特許権者Aさんが望んでいなくても第三者Cさんに発明を実施させなくてはならない場面があります。これが法定通常実施権や裁定通常実施権になります。
法定通常実施権は法律によって発生する通常実施権で先使用権などが代表的なものです。裁定通常実施権は裁定という手続きで発生する通常実施権です。
また通常実施権の中には無償で実施できるものと相当の対価を支払わなくては実施できないものが存在します。
さてみなさんは特許法の通常実施権の中で相当の対価を支払わなくてはならないものを瞬時に言えますか?
先願優位の原則から考えていけば、だいたいわかるところなんですがなかなかすぐには出てこないですよね!
通常実施権の中で相当の対価を支払わなくてはならないものの語呂
安心してください。これには語呂合わせがあります。

泣くに昼夜に、金払え
なくに 79条の2(移転登録前の実施による通常実施権)
ちゅう 中用権(80条)
やに 82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権の専用実施権者、通常実施権者)
金払え 相当の対価が必要
この語呂合わせの場合、金払えの部分で使用する場面が想起できるのでとても使いやすいですね。
でも、やに(82条)ってなんだっけってなりそうです。
48条の3第8項の通常実施権について
ちなみに受験生時代なんとなく違和感を感じていましたが48条の3第8項の通常実施権は対価が不要です。
48条の3第8項の通常実施権は審査請求期間が経過して取下げ擬制された出願が、期間内に審査請求できない正当な理由があったことが認められて審査請求され登録された場合に認められるものです。
ちょっとドラマ仕立てで考えてみましょう。
お、今日特許公報みたら甲さんの発明Aの出願が審査請求されず取下げ擬制されとったぞ。
発明Aは当社も実施したかったから助かった。早速装置を購入して実施しよう。
ーーーーーーーーーーーー数か月後ーーーーーーーーーー
あれ、今日 特許公報を見たら甲さんの発明Aに5項の規定による出願審査の請求があったみたいだぞ。
もう装置購入してしまったし登録されたたら無駄になってしまうどうしよう。。。
ーーーーーーーーーーーー数か月後ーーーーーーーーーー
うわ、甲さんの発明A が登録になってしまったよ。
せっかく装置入れたのに実施できないの?
このドラマでかぶりさんは、特許公報を信じて発明Aの実施のため投資に踏み込んだのですが結果的に大損をしてしまいます。しかし48条の3第8項の通常実施権を有することすれば 引き続き 発明A を実施できます。ここまでは納得できます。
次にかぶりさんが対価を払うべきかについてです。青本の中用権(80条)の部分では、公平の観念の場合は対価は不要で、設備保護の場合は対価が必要と記載されています。ここから考えても対価の支払いがあっても良いように思えます。ここを説明できる方がいたら教えてほしいです。
ただしテスト的には48条の3第8項の通常実施権は対価が不要です。 条文に記載がないからです。
念を押すのための根拠としては改正本にある次の記載です。
当該通常実施権を有する者は、先使用(同法第79条)等と同様に、その出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位を有するため、補償金(同法第65条第1項)を支払う義務を負わないことから、当該通常実施権を有する者に対する補償金請求権の制限について明文規定は設けないこととした。
引用元:特許法第 48条の3第8項
相当の対価ではなくて補償金請求権の制限と書かれていますが対価も不要なのでしょう。
特許法142条 除斥忌避の申立方法
審判における除斥忌避の申立方法の覚え方についてです。
突然ですが審判の場面で
①参加の申請
②除斥忌避の申立
書面でも口頭でも申請(申立)できるものはどちらでしょう?
答えは 除斥忌避の申し立て です。
パッと答えられなかった人は、覚え方(語呂合わせ)を解説しますので最後まで読んでください。
除斥とは
除斥とは当事者等の身内などが審判官(審査官)の職務の執行から除斥される制度です。
具体的にどのような人が除斥されるのかは特許法139条各号に規定されています。
審判の公正を確保するためこのような規定が設けられています。
特許法139条各号の審判官は職務の執行から当然に除斥されます。
特許法140条で除斥の申立てが一応できるようになっていますが、これは確認的に規定されているだけで本来は申立てなんてしなくても除斥されていなければなりません。
忌避とは
忌避とは審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときに当事者等が申し立てて、 審判官に職務の執行から外れてもらう制度です。
除斥と違って申立てがあって、決定があって初めて忌避されることになります。
審判の公正を妨げるべき事情 というのは、結婚はしていないけど、婚約しているなど客観的合理的な理由が必要です。
公正に判断してくれない審判官に審判を頼みたくないので、忌避の申立をして外れてもらうのです。
審判における様々な申し立てや申請
審判の場面では、様々な申立てや申請が可能です。
・参加の申請
・除斥忌避の申立て
・証拠調べ、証拠保全の申立て
・書面審理の申立て
参加申請については、特許法の第149条に次のように記載されています。
参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
なので口頭で申請をすることはできません。
ちなみに民事訴訟法では、口頭書面どちらでも可能ですが特許法では書面に限定しています。
平成29年弁理士試験 短答式試験の第15問の3でも以下のように問われています。【特許・実用新案】第15問
特許法に規定する審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
3、特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。
引用元: 平成29年度弁理士試験 短答式筆記試験問題
答え、×
また参加申請書は、審判長に提出します。
一方で除斥忌避については、原則は書面としてながらも口頭での申し立てを認めています。
特許法 第142条1項の規定を見てみましょう。
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる
引用元:特許法 第142条1項
とあります。
さらに、その申し立ての相手は「特許庁長官」です。
除斥忌避の申立て方法の語呂
上述したように参加の申請と除斥忌避の申立ては、細かい違いがあってごっちゃになってしまうことが多いです。そんな方は次の語呂合わせを活用しましょう。
高所(恐怖症)のジョッキー朝刊へ

高所恐怖症のジョッキーが、そんなハンデギャップに打ち勝って1着になり朝刊を飾ったシーンを想像しよう。
高所 口頭、書面
ジョッキー 除斥忌避
朝刊へ 特許庁長官
①除斥又は忌避の申立は口頭でも書面でもできること
②特許庁長官にすること
が手軽に覚えられます。![]()
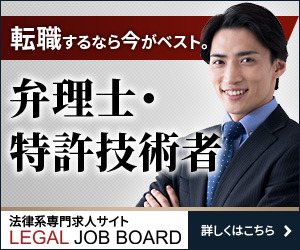



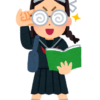



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません